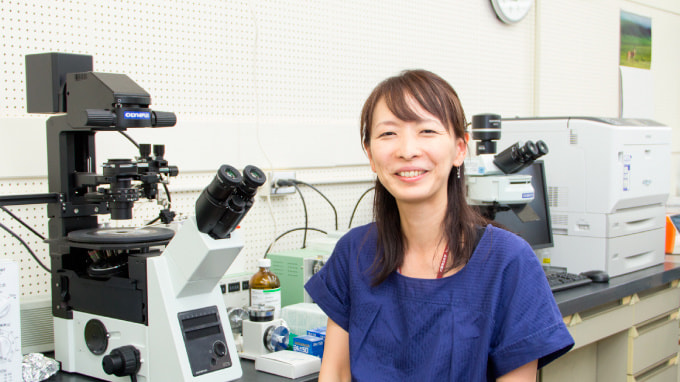MESSAGE |
/ メッセージ |
|---|
私たちは、老化および感染のメカニズム、制御方法について、線虫C. elegansをモデルとした研究を行っています。センチュウと聞くとヒトとはかけ離れた存在のように感じられるかもしれませんが、ヒト遺伝子の約70%は線虫にもあります。そして実は数々のノーベル賞研究に貢献してきた生き物なのです。また近年、炎症は感染のみならず、さまざまな慢性疾患と密接に関わることが明らかになってきています。私たちはマウス病態モデルも駆使しながら、腸内細菌を利用した炎症抑制の可能性にも注目して研究を進めています。ぜひ、皆さんも一緒に研究してみませんか?
教授
中台(鹿毛)枝里子